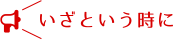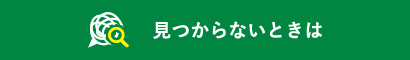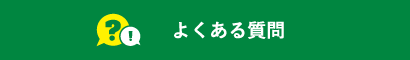コラム「高原町の歴史(町内の地名編5)」
町内の地名はいつからあるの?(その5)
すいません、前回更新から2ヶ月も開いてしまいました。
さて、前回から何度も登場する『高原所系図壱冊』、翻刻したものは町HPに無料公開しておりますので、詳細を知りたい方はご自由にご覧下さい。現代語訳はしてませんが、読み進めるうちに、何となく理解はできると思います。前半は、「誰が高原に入って、誰が出て行った」の記事が中心なので、あまりおもしろくありませんが、江戸時代中期辺りからリアルタイムで起こった出来事を書いているので、俄然おもしろくなります。
今日は、幕末の一記事から。
一 慶應三年丁卯正月十一日宮田之上幷木之移百性甚太郎等申者
養女牛子産申候処、躰壱ツ、四足、尾壱ツ、首より両ツニ相成頭両ツ之
面、口二ツニはおゑ、はな二ツ、目四ツ、みミ四ツ、角四ツある、両之頭ふとき
たらさる 所なく手生候月数相合候故不足なく、黒牛生候処、四五日も相掛候得者、
うミころし候而も城下江御披露ニ相成候、右之次第人暦之巻ニ相見得人皇六拾九代後
朱雀院之代長久四年癸未之歳、牛両之頭有子ヲうむと相見得候、此年大ひてり
時は慶応3年(1867)正月、「宮田之上幷木」の移百姓の甚太郎の養女が「牛子」を出産したとの事。ここで登場する「宮田」は、今の「宮田ん坂」「宮田ん迫」と呼ばれている辺り、昔は「宮田村」があったそうです。戦国時代末期に高原で活躍した宮田飛騨守政次の住まう土地でした。その上にある「幷木」、これが現在の並木地区という事になります。そこの「移百姓」の事ですが、これは当時の薩摩藩の政策「人配(にんべ)」と呼ばれる、薩摩半島から新田開発に伴い移住させられた人達を指しています。並木地区は今も薩摩川内方面から移住してきたという伝承を持っています。
さて、移百姓の養女が「牛子」を産んだ、と。その様は双頭の黒牛であったようです。結局はすぐに死んだようで、珍しさもあって鹿児島城下で披露する事になった、とありますが、実際どうなったかは不明です。
人が産んだ不思議な「双頭の牛」ですが、第69代朱雀天皇の時にも同じような事があったとか。『扶桑略記 巻廿八』によると、長久4年(1043)に同じような双頭の牛が産まれたようです。
余談ですが、こういった牛にまつわる怪異と言えば「件(くだん)」と呼ばれる、顔は人で体が牛、あるいは「牛女」とも呼ばれる、顔が牛で体が女性(多くが女性用の着物を着ている)、が有名です。県北にも「件」のほんの少しですが伝承があったそうです。
(文責 大學 康宏)
さて、前回から何度も登場する『高原所系図壱冊』、翻刻したものは町HPに無料公開しておりますので、詳細を知りたい方はご自由にご覧下さい。現代語訳はしてませんが、読み進めるうちに、何となく理解はできると思います。前半は、「誰が高原に入って、誰が出て行った」の記事が中心なので、あまりおもしろくありませんが、江戸時代中期辺りからリアルタイムで起こった出来事を書いているので、俄然おもしろくなります。
今日は、幕末の一記事から。
一 慶應三年丁卯正月十一日宮田之上幷木之移百性甚太郎等申者
養女牛子産申候処、躰壱ツ、四足、尾壱ツ、首より両ツニ相成頭両ツ之
面、口二ツニはおゑ、はな二ツ、目四ツ、みミ四ツ、角四ツある、両之頭ふとき
たらさる 所なく手生候月数相合候故不足なく、黒牛生候処、四五日も相掛候得者、
うミころし候而も城下江御披露ニ相成候、右之次第人暦之巻ニ相見得人皇六拾九代後
朱雀院之代長久四年癸未之歳、牛両之頭有子ヲうむと相見得候、此年大ひてり
時は慶応3年(1867)正月、「宮田之上幷木」の移百姓の甚太郎の養女が「牛子」を出産したとの事。ここで登場する「宮田」は、今の「宮田ん坂」「宮田ん迫」と呼ばれている辺り、昔は「宮田村」があったそうです。戦国時代末期に高原で活躍した宮田飛騨守政次の住まう土地でした。その上にある「幷木」、これが現在の並木地区という事になります。そこの「移百姓」の事ですが、これは当時の薩摩藩の政策「人配(にんべ)」と呼ばれる、薩摩半島から新田開発に伴い移住させられた人達を指しています。並木地区は今も薩摩川内方面から移住してきたという伝承を持っています。
さて、移百姓の養女が「牛子」を産んだ、と。その様は双頭の黒牛であったようです。結局はすぐに死んだようで、珍しさもあって鹿児島城下で披露する事になった、とありますが、実際どうなったかは不明です。
人が産んだ不思議な「双頭の牛」ですが、第69代朱雀天皇の時にも同じような事があったとか。『扶桑略記 巻廿八』によると、長久4年(1043)に同じような双頭の牛が産まれたようです。
余談ですが、こういった牛にまつわる怪異と言えば「件(くだん)」と呼ばれる、顔は人で体が牛、あるいは「牛女」とも呼ばれる、顔が牛で体が女性(多くが女性用の着物を着ている)、が有名です。県北にも「件」のほんの少しですが伝承があったそうです。
(文責 大學 康宏)