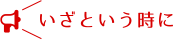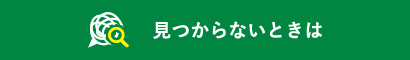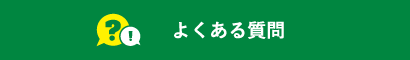コラム「高原町の歴史(歴史編その1)」
「狭野の杉並木」が天然記念物に指定されて101周年(?)
「狭野の杉並木」と言えば、高原町を代表する文化財で、大正13年(1924)12月9日に国の天然記念物に指定されました。
昨年の令和6年(2024)、指定されてからちょうど100年を迎えていたんですね。まあ、東京都の府中市から電話があって初めて知ったのですが。大正13年、高原町や府中市をはじめ複数市町村で巨木の並木が国の指定になったようです。
この「狭野の杉並木」ですが、どこからどこまでが指定範囲なのか。当時の史料を見ると、所在地は「狭野神社境内」、指定範囲は「参拝道の両側 壹町貳段七畝八歩」とあるだけ。結局、最初何本あったのかは全く不明。昭和10年(1935)刊行の『高原郷土史』には、「十字路広場の左に杉の巨樹が37本あったが、往年の暴風で破損し、今生存するのは十数本」とあります。さらに、狭野神社の調査文書から引用して、「合計933本」としています。但しこの数値は、明らかに巨樹ではない感じの木も含まれているので、指定当時どれぐらいあったのかは不明です。
さて問題は、植えられた年代。指定当時の史料には全く書かれていません。前述の『高原郷土史』では、「島津義弘が朝鮮に出兵する際に狭野社へ戦勝祈願に来た。」「凱旋後、慶長年間に祈願奉賽して新納武蔵守を使わして境内全般に杉を植栽して奉納した」とあります。となると、慶長年間だから1596年~1615年の間。「凱旋後」とありますが、島津義弘は文禄・慶長どちらも渡海しているので、文禄の役と慶長の役の間の慶長元年(1596)、慶長の役から帰って来た慶長3年(1598)頃。翌4年は庄内の乱、5年関ヶ原の戦と、怒濤のゴタゴタが続くので、のんびり植える暇があるか、等々と推測してみると、『高原郷土史』に書いている内容って、どの文献から引用したのかが全く書いていないので、実際に引用したのか、作者の超推理なのか、わからない事が多すぎるのです。
今のところ有益な史料としては、鹿児島県史料『斉彬公史料一』に収録されている「三三九 大隅国肝属郡其他日州諸縣郡諸郷御巡見ノ事実」が唯一かな、と。これは、嘉永6年(1853)、江戸から薩摩国入りした藩主の島津斉彬が大隅国と日向国を巡見した時の記事です。その際、高原郷の狭野社にも参詣し大杉を見た島津斉彬は、「社殿近傍の大杉は、島津義弘公が朝鮮渡海前に戦勝祈願のため自ら植えた」「社道左右の大杉も、随行の武士1人につき2本ずつ植えた」「そういう由緒があるから義弘はそれを懐かしみ、丁寧に保護するよう特命した」という話を聞いたようです。
この話を事実とするなら、植えたのは動員が発令された天正19年(1591)から文禄元年(天正20年・1592)の渡海直前かな、と。
ここで気付くのは、島津義弘が植えたのは「社殿近傍」、義弘家臣が植えたのは「社道(参道)左右」、国の天然記念物に指定されているのは家臣が植えた方で、義弘が植えたとされている杉は、全く指定に含まれていない事です。
現在、社殿の近くに1本の大杉がありますが、ひょっとしたら、これが義弘手植えの杉かもしれません。
(文責 大學 康宏)
昨年の令和6年(2024)、指定されてからちょうど100年を迎えていたんですね。まあ、東京都の府中市から電話があって初めて知ったのですが。大正13年、高原町や府中市をはじめ複数市町村で巨木の並木が国の指定になったようです。
この「狭野の杉並木」ですが、どこからどこまでが指定範囲なのか。当時の史料を見ると、所在地は「狭野神社境内」、指定範囲は「参拝道の両側 壹町貳段七畝八歩」とあるだけ。結局、最初何本あったのかは全く不明。昭和10年(1935)刊行の『高原郷土史』には、「十字路広場の左に杉の巨樹が37本あったが、往年の暴風で破損し、今生存するのは十数本」とあります。さらに、狭野神社の調査文書から引用して、「合計933本」としています。但しこの数値は、明らかに巨樹ではない感じの木も含まれているので、指定当時どれぐらいあったのかは不明です。
さて問題は、植えられた年代。指定当時の史料には全く書かれていません。前述の『高原郷土史』では、「島津義弘が朝鮮に出兵する際に狭野社へ戦勝祈願に来た。」「凱旋後、慶長年間に祈願奉賽して新納武蔵守を使わして境内全般に杉を植栽して奉納した」とあります。となると、慶長年間だから1596年~1615年の間。「凱旋後」とありますが、島津義弘は文禄・慶長どちらも渡海しているので、文禄の役と慶長の役の間の慶長元年(1596)、慶長の役から帰って来た慶長3年(1598)頃。翌4年は庄内の乱、5年関ヶ原の戦と、怒濤のゴタゴタが続くので、のんびり植える暇があるか、等々と推測してみると、『高原郷土史』に書いている内容って、どの文献から引用したのかが全く書いていないので、実際に引用したのか、作者の超推理なのか、わからない事が多すぎるのです。
今のところ有益な史料としては、鹿児島県史料『斉彬公史料一』に収録されている「三三九 大隅国肝属郡其他日州諸縣郡諸郷御巡見ノ事実」が唯一かな、と。これは、嘉永6年(1853)、江戸から薩摩国入りした藩主の島津斉彬が大隅国と日向国を巡見した時の記事です。その際、高原郷の狭野社にも参詣し大杉を見た島津斉彬は、「社殿近傍の大杉は、島津義弘公が朝鮮渡海前に戦勝祈願のため自ら植えた」「社道左右の大杉も、随行の武士1人につき2本ずつ植えた」「そういう由緒があるから義弘はそれを懐かしみ、丁寧に保護するよう特命した」という話を聞いたようです。
この話を事実とするなら、植えたのは動員が発令された天正19年(1591)から文禄元年(天正20年・1592)の渡海直前かな、と。
ここで気付くのは、島津義弘が植えたのは「社殿近傍」、義弘家臣が植えたのは「社道(参道)左右」、国の天然記念物に指定されているのは家臣が植えた方で、義弘が植えたとされている杉は、全く指定に含まれていない事です。
現在、社殿の近くに1本の大杉がありますが、ひょっとしたら、これが義弘手植えの杉かもしれません。
(文責 大學 康宏)