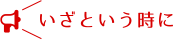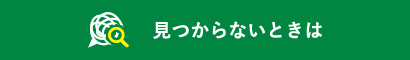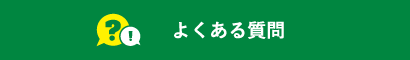コラム「高原町の歴史(新燃岳の享保噴火その2)」
新燃岳の享保噴火について(その2)
さて、新燃岳は、約2000~6000年前に噴火したという事ですが、その後大きな噴火をしたのが享保元年(1716)から2年(1717)、文政4年(1822)、昭和34年(1959)。今回は昭和の噴火に触れましょう。
昭和の噴火では、昭和34年2月13日と17日に大きな噴火があったそうです。ただ、『広報たかはる』昭和34年4月号には17日の噴火しか記されておらず、その後は噴煙が見られる程度で、そのまま沈静化したようです。
『広報たかはる』同年3月号によると、全く予想できなかったその時の噴火は、折からの雨雲を伴った南西の風により町内の8割が降灰の被害に見舞われ、道路は泥土に、農作物にも灰が付着したようです。その時の思い出話で、水を含んだ灰にまみれた鳥が飛ぶこともできず、地を這い回っているのを見たという話を聞きました。同じく広報では、農作物の被害額は当時の価格で約9500万円、その時期の農作物の麦などは約5割が被害にあった他、シイタケや澱粉、牛乳等にも大きな被害があったようです。
17日以後、噴火は終息したものの、いつ噴火するかもわからないという事で、福岡気象台から観測機器を借用して庁舎に設置することになったそうです(その後の広報紙がないため、詳細は不明ですが)。
(文責 大學 康宏)
昭和の噴火では、昭和34年2月13日と17日に大きな噴火があったそうです。ただ、『広報たかはる』昭和34年4月号には17日の噴火しか記されておらず、その後は噴煙が見られる程度で、そのまま沈静化したようです。
『広報たかはる』同年3月号によると、全く予想できなかったその時の噴火は、折からの雨雲を伴った南西の風により町内の8割が降灰の被害に見舞われ、道路は泥土に、農作物にも灰が付着したようです。その時の思い出話で、水を含んだ灰にまみれた鳥が飛ぶこともできず、地を這い回っているのを見たという話を聞きました。同じく広報では、農作物の被害額は当時の価格で約9500万円、その時期の農作物の麦などは約5割が被害にあった他、シイタケや澱粉、牛乳等にも大きな被害があったようです。
17日以後、噴火は終息したものの、いつ噴火するかもわからないという事で、福岡気象台から観測機器を借用して庁舎に設置することになったそうです(その後の広報紙がないため、詳細は不明ですが)。
(文責 大學 康宏)