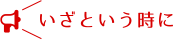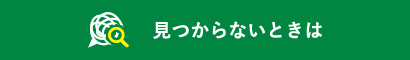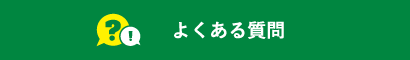コラム「高原町の歴史(新燃岳の享保噴火その5)」
新燃岳の享保噴火について(その5)
さて、2月・3月の噴火を取り上げました。噴火した事はわかるものの、被害等はボヤッとしています。まあ、その後も生活しているので、さほどの被害はなかったのかもしれません。
次に文献で確認される噴火は8月。3月からずいぶん時間が経ちました。何度も登場する地元文献『高原所系図壱冊』には登場しないんですね。登場するのは、一つはここではお馴染みの『古今山之口記録』。「八月十一日、霧島山大燃ニ而当地江茂壱歩ニ砂灰壱升三合降る」とあります。山之口郷のおもしろいところは、「灰がいっぱい降った」という漠然とした記述でなく、降灰した量を計測している所。「壱歩」は約3.3平方メートルで一坪、つまり一坪辺り砂灰が一升三合、2リットルのペットボトルが溢れるぐらい降ったという意味になります。一升三合と聞くとかなり多いように思えますが、一坪辺りと考えると、1~2cmといったところでしょうか。
もう一つの文献は『三州御治世要覧附録 年代記』。これは、鹿児島城下士の清水盛富が宝暦5(1755)年に編纂したものと、安永7(1778)年に追筆増補したものがあります。ただ、この書物、清水盛富の系譜も執筆された理由も不明な部分が多くて、今のところどう評価したら良いのかわからない部分もあります。明らかに『古今山之口記録』閲覧できる立場に居るような記述もあれば、やたら伝聞口調の記述が混然しているので。
その『年代記』には「八月十一日、霧嶋山大燃、朝七ッ半より五ッ比迄硫黄瀬泥ニ而、高原・狭野原・蒲牟田・櫟原壱尺余降埋候」とあります。8月11日は同じなのですが、こちらは「朝七ッ半より五ッ比迄」午前5時頃から8時ぐらいまで、といったところでしょうか。続きは「硫黄瀬泥ニ而、高原・狭野原・蒲牟田・櫟原壱尺余降埋候」とあります。硫黄瀬というのが場所なのか不明ですが、硫黄の臭いがきつい泥と解釈した方が良いでしょうか。その後は、高原や狭野原・蒲牟田に一尺ほど降ったとありますが、ここでは灰と解釈して良いのでは、と思います。問題は「櫟原」という地名。『年代記』には「クヌキ(はら)」とルビが振られています。高原に住む人なら「どこだよ?」と思いますよね。そんな地名ないですし。後、一尺も降ればたいがいな被害かと思うのですが、何で地元の文献にこの記述が無いのか、色々と疑問は尽きません。
(文責 大學 康宏)
次に文献で確認される噴火は8月。3月からずいぶん時間が経ちました。何度も登場する地元文献『高原所系図壱冊』には登場しないんですね。登場するのは、一つはここではお馴染みの『古今山之口記録』。「八月十一日、霧島山大燃ニ而当地江茂壱歩ニ砂灰壱升三合降る」とあります。山之口郷のおもしろいところは、「灰がいっぱい降った」という漠然とした記述でなく、降灰した量を計測している所。「壱歩」は約3.3平方メートルで一坪、つまり一坪辺り砂灰が一升三合、2リットルのペットボトルが溢れるぐらい降ったという意味になります。一升三合と聞くとかなり多いように思えますが、一坪辺りと考えると、1~2cmといったところでしょうか。
もう一つの文献は『三州御治世要覧附録 年代記』。これは、鹿児島城下士の清水盛富が宝暦5(1755)年に編纂したものと、安永7(1778)年に追筆増補したものがあります。ただ、この書物、清水盛富の系譜も執筆された理由も不明な部分が多くて、今のところどう評価したら良いのかわからない部分もあります。明らかに『古今山之口記録』閲覧できる立場に居るような記述もあれば、やたら伝聞口調の記述が混然しているので。
その『年代記』には「八月十一日、霧嶋山大燃、朝七ッ半より五ッ比迄硫黄瀬泥ニ而、高原・狭野原・蒲牟田・櫟原壱尺余降埋候」とあります。8月11日は同じなのですが、こちらは「朝七ッ半より五ッ比迄」午前5時頃から8時ぐらいまで、といったところでしょうか。続きは「硫黄瀬泥ニ而、高原・狭野原・蒲牟田・櫟原壱尺余降埋候」とあります。硫黄瀬というのが場所なのか不明ですが、硫黄の臭いがきつい泥と解釈した方が良いでしょうか。その後は、高原や狭野原・蒲牟田に一尺ほど降ったとありますが、ここでは灰と解釈して良いのでは、と思います。問題は「櫟原」という地名。『年代記』には「クヌキ(はら)」とルビが振られています。高原に住む人なら「どこだよ?」と思いますよね。そんな地名ないですし。後、一尺も降ればたいがいな被害かと思うのですが、何で地元の文献にこの記述が無いのか、色々と疑問は尽きません。
(文責 大學 康宏)