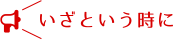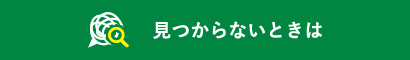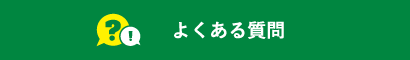令和7年度個人住民税の定額減税について
令和7年度個人住民税の定額減税について
令和6年度の個人住民税において、対象にならなかった控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。
(注)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者:前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方。
定額減税の対象者
令和7年度の個人住民税の定額減税は、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象となります。
定額減税額
令和7年度の個人住民税所得割から1万円が控除されます。
ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
(注1)令和7年度のみの適用となります。
(注2)均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。
定額減税の控除方法
令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
注意事項
定額減税額については、納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書の摘要欄に記載しています。
定額減税は、住宅借入金等特別税額控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
寄附金税額控除の特例控除の上限額については、定額減税前の所得割額をもとに算定されます。
定額減税を装った詐欺にご注意ください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
定額減税に関して、町がATMの操作や手数料の振り込みをお願いすることはありません。被害に遭わないために、怪しい電話がかかってきた場合は、家族や知人、警察に相談しましょう。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください [PDFファイル/449KB]
定額減税についてよくある質問
Q.定額減税の対象となる方の条件を教えてください
A.令和7年度の個人住民税が課税される方で、令和6年分の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下であり、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の方)がいる方が対象となります。
Q.定額減税を受けるために、何か申請は必要ですか
A.定額減税を受けるための申請は必要ありません。
税務署に提出された令和6年分所得税確定申告書や勤務先から提出された令和7年度給与支払報告書などを基に定額減税の摘要の有無を判断します。
Q.定額減税により控除された額は、何を見れば確認できますか
A.高原町から通知する町民税・県民税・森林環境税の納税通知書等をご確認ください。
普通徴収の方・公的年金から特別徴収される方→令和7年6月にお送りする納税通知書等をご覧ください。
給与から特別徴収される方→令和7年5月に勤務先を通じてお送りする特別徴収税額の決定通知書をご覧ください。
Q.令和6年中に所得がなかったため、令和7年度の町県民税は非課税ですが、定額減税の適用は受けられないのでしょうか
A.町県民税の所得割が課税されていない方は、定額減税の対象となりません。
Q.私の令和6年分の合計所得金額が1,000万円以下ですが、扶養している配偶者は定額減税の対象にならないのでしょうか
A.納税義務者(本人)の合計所得金額が1,000万円以下の場合は、扶養している配偶者は「控除対象配偶者」に該当し、令和7年度の定額減税の対象となる「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に該当しないため、定額減税は適用されません。
なお、「控除対象配偶者」は令和6年度の定額減税の対象となっています。
Q.令和7年に結婚し、配偶者を扶養していますが、同一生計配偶者に該当しますか
A.令和7年度の町県民税における同一生計配偶者に該当するかどうかは、令和6年末時点の状況により判定しますので、令和7年中に結婚し、扶養することとなった配偶者は同一生計配偶者に該当しません。
Q.令和6年中に亡くなった配偶者を亡くなるまで扶養してましたが、同一生計配偶者に該当しますか
A.令和7年度の町県民税における同一生計配偶者に該当するかどうかは、令和6年中に亡くなった方の場合、亡くなった時点の状況により判定しますので、同一生計配偶者に該当します。
関連リンク
個人住民税の定額減税に係るQ&A集(総務省)<外部リンク>
国税庁 定額減税特設サイト<外部リンク>