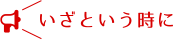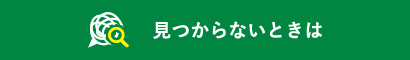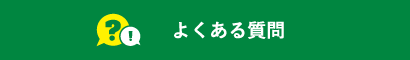高原町における河川及び御池の水質検査結果について
高原町では、高原町河川愛護条例に基づいて、河川水質の状況を把握するために、町内5河川(高崎川、高千穂用水、前田迫川、岩瀬川、炭床川)及び御池について年4回水質検査を実施しています。
環境基準について
河川の水質環境基準は、環境基本法に基づいて生活環境を保全するうえで維持されることが望ましいものとして5項目について定められています。
生活環境の保全に関する環境基準
生活環境項目は利水目的に応じて水域類型が定められており、水域の類型毎に基準が設定されています。
| 項目 類型 | 利用目的の 適応性 |
基 準 値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度 (Ph) |
生物化的 酸素要量 (Bod) |
浮遊物量 (Ss) |
溶存酸量 (Do) |
大腸菌群数 | ||
| Aa | 水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの |
6月5日以上 8月5日以下 |
1mg/l 以下 |
25mg/l 以下 |
7月5日mg/l 以上 |
50Mpn/ 100ml以下 |
| A | 水道2級 水産1級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの |
6月5日以上 8月5日以下 |
2mg/l 以下 |
25mg/l 以下 |
7月5日mg/l 以上 |
1,000Mpn/ 100ml以下 |
| B | 水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの |
6月5日以上 8月5日以下 |
3mg/l 以下 |
25mg/l 以下 |
5mg/l 以上 |
5,000Mpn/ 100ml以下 |
| C | 水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの |
6月5日以上 8月5日以下 |
5mg/l 以下 |
50mg/l 以下 |
5mg/l 以上 |
- |
| D | 工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの |
6.0以上 8月5日以下 |
8mg/l 以下 |
100mg/l 以下 |
2mg/l 以上 |
- |
| E | 工業用水3級 環境保全 |
6.0以上 8月5日以下 |
10mg/l 以下 |
ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/l 以上 |
- |
| 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 全窒素 | 全リン | ||
| I | 自然環境保全及びIi以下の欄に掲げるもの | 0.1mg/L以下 | 0.005mg/L下 |
| Ii | 水道1,2,3級(特殊なものを除く。)水産1種水浴及びIii以下の欄に掲げるもの | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
| Iii | 水道3級(特殊なもの)及びIv以下の欄に掲げるもの | 0.4mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
| Iv | 水産2種及びVの欄に掲げるもの | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
| V | 水産3種工業用水農業用水環境保全 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
(注)
- 水道1級・・・ろ過等による簡易な浄化操作を行うもの。
- 水道2級・・・沈殿ろ過等による通常の浄化操作を行うもの。
- 水道3級・・・前処理などを伴う高度の浄水操作を行うもの。
- 水産1級・・・ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用。
- 水産2級・・・サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水生生物用。
- 水産3級・・・コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用。
- 工業用水1級・・・沈殿等による通常の浄水操作を行うもの。
- 工業用水2級・・・薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの。
- 工業用水3級・・・特殊の浄水操作を行うもの。
調査項目ついて
Ph(水素イオン指数)
液体中の水素イオン濃度をあらわす値。7を中性とし、7より大きいものをアルカリ性、小さいものが酸性となります。
Do(溶存酸素)
液中あるいは水中に溶解している分子状酸素の濃度をあらわす値。汚れた水に溶存酸素は少なく、2mg/l以下で悪臭が出るとされています。魚が生存するためには最低5ppm必要とされています。
※1ppm=0.0001%
Bod(生物化学的酸素要求量)
水の汚染度を示す主要指標で、汚物が水中で分解(好気性バクテリアによって酸化され、硝酸、亜硝酸または酸化ガス、窒素、炭素等に分解される)されるのに必要な酸素の量をあらわす値。この数値が大きいほど汚染度は高く、10ppm以上になると異臭がします。5ppmで鯉や鮒、3ppm以下で鮎が住めるといわれています。
Codmn(化学的酸素要求量)
Bodと同じく水の汚染度を示す主要指標とされています。水中に含まれる被酸化性物質量を酸化(分解)するために必要とする酸素の量であらわした値。この値が大きいほど、水中に分解されるべき物質が多く、水質の汚染度が高いということになります。一般的に5ppm以下が望ましいとされています。Bodが生物分解性(有機物)の酸素要求量をあらわす値であるのに対し、Codは有機物と無機物両方の酸素要求量をあらわしています。
Ss(浮遊物質)
水中に浮遊、懸濁(けんだく)している汚濁物質の量をあらわす値。値が大きいほど汚染度は高く、正常な生産活動を行うには25ppm以下、農業用水として使用する場合には10ppm以下である必要があるとされています。
大腸菌郡数
大腸菌及び大腸菌と性状の似た細菌の総称。水中の大腸菌郡数は、し尿汚染の指標とされています。
単位Mpn/100mlについて
Mpnとは、「Most Probable Number」の略で、「才確数」の意味です。大腸菌の測定は、「特定酵素基質培地法」という方法で行われます。測地したい水を培養皿に取って水中の大腸菌を培養し、そのコロニー(集落)数を数えて測定します。最確数とは、コロニーの数を確率として統計学的に表したもののことで試験対象の水100mlに対して培養されたコロニーが10個であれば「10Mpn / 100ml」ということになります。
全窒素(T-N)
湖沼及び海域の水質調査項目。窒素化合物の総量で、富栄養化の原因となります。
※富栄養化・・・植物プランクトンの増加によって赤潮が発生し、養殖漁業や景観への被害を招きます。
リン酸イオン
家庭からの生活排水、特に科学洗剤を使用後の雑排水に多く含まれています。リン酸イオンが多量に湖沼に流入すると富栄養化が進み、アオコなどの植物性プランクトンが大量に発生し、他の水生の動植物に被害を及ぼすとされています。
全リン(T-P)
湖沼及び海域の水質調査項目。リン化合物の総量で富栄養化の原因となります。
クロロフィル
湖沼及び海域の水質調査項目。クロロフィルは、植物に含まれている葉緑素の一種であり、水中のクロロフィルを測定することにより、植物プランクトン(藻類)の発生状況を知ることができます。
湖沼の栄養階級区分
| 項目 | 貧栄養湖 | 中栄養湖 | 富栄養湖 |
|---|---|---|---|
| クロロフィルa[mg/m3] | 0.3~3 | 2~15 | 10~500 |
※富栄養湖・・・全体に栄養物質に富み,植物が多く,生物生産の大きな湖。夏期、プランクトンの繁殖が著しく,水の華(はな)を生ずる。透明度5m以下。
※貧栄養湖・・・栄養物質が全体に少なく、生物生産の小さい湖。透明度5m以上。