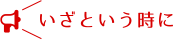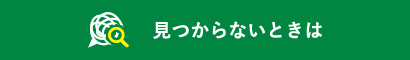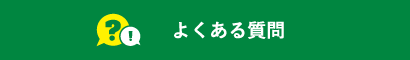町の歴史
高原町の歴史を訪ねて
1. 神話
江戸時代末期に薩摩藩により編纂された『三国名勝図會』には、高原の名称に次のように記されています。
土俗傳へ云、當邑を高原と號するは高天原の略称なりと、凡日向国内此辺は、神代の 皇都に係り、今に都島都島は今の都城、
高城などといへる地名殘るも此が為にて、此地、都島と接し(後略)、
これによると、「高原」という地名は「高天原」から転じたものであるとの事です。高千穂峰の山頂には、高天原からニニギノミコトが降臨される際に突き刺したとされる「天の逆鉾」があります。旅行記により17世紀半ばにはその存在を確認することができます。
また、高原には「神武天皇御降誕の地」という伝承もあります。『日本書紀』にある神武天皇の幼名「狭野尊」が当町の狭野地区を指しているというのが主な根拠で、生誕から東征までこの地で暮らしたというものです。
前述の『三国名勝図會』にもその伝承が記されていますが、新燃岳の享保噴火(1716~1717)の直後に作成された神社文書を見ると、現在の伝承地あたりは詳細不明ながらも「聖蹟」と認識されていた事がわかります。
2. 古墳時代以前
まず、高原町では、旧石器時代の遺跡は確認されていない。現在のところ確認できた最も古い遺跡は縄文時代前期である。後川内地区の川除遺跡からは曽畑式及び轟B式土器が数点確認された。又、大谷遺跡では、表採資料の中に曽畑式が数点確認された。現在のところ、この2遺跡のみである。
縄文時代中期になると、徐々に遺跡が増加する。昭和43年に発掘調査された高原畜産高校遺跡や椨粉山遺跡などで阿高式土器が出土した。
縄文時代中期末から後期に入り、遺跡の数が増大する。主な遺跡としては、大谷・佐土・椨粉山遺跡などがある。それらの遺物には、南九州の在地文化から中~北部九州・瀬戸内・四国など、幅広い文化圏の影響が見られる。
その後、遺跡数が急激に減少し、弥生時代の遺跡は殆ど見られない。これは調査数の少なさによる。弥生時代から古墳時代にかけての集落遺跡が調査されたのは、麓地区の立山・荒迫遺跡のみである。このうち立山遺跡では、弥生時代後期から古墳時代初頭の住居跡が30基近く検出され、さらに軽石製の炉や埋甕などが検出された。
高原町における古墳時代の遺跡は、集落遺跡よりも地下式横穴墓の方が著名である。高原町では、これまでに4群107基が検出されている。出土地は、湯之崎・旭台・日守・立切で、後川内に多い。墓内の家屋表現や彩色がよく見られる。西都原古墳群のような高塚古墳は見られないが、山間部には墳丘と思われるマウントが多く見られる。
3. 古代
地下式横穴墓の下限である6世紀前半から歴史的に全くの空白となる。照葉樹林や草原を形成していた事が土壌分析により判明している。
9世紀に入ると、同時多発的に開墾が行われている。荒迫・川除・大谷・椨粉山遺跡で畝状遺構が検出された。栽培作物については多少のイネの痕跡が見られる程度で、大方は根菜類の可能性が高い。
この畠が使用されなくなった後は、再び山林化し、鎌倉時代から中世にかけては、荒迫・大鹿倉・椨粉山・宇津木遺跡などで狩猟用と見られる陥し穴が数多く検出されている。
なお、この辺りから霧島山に関する記述が見られるようになる。承和4年(837)には官社に列せられて従五位上の位が与えられ(『続日本後紀』)、続く天安2年(858)には従四位下に昇格した(『日本三代実録』)。この時は「霧島岑神」と称されている。又、『延喜式』には、諸縣郡一座として霧嶋神社の名が挙がっている。
承平5年(935)頃に成立したとされる『倭名類聚抄』には、「諸縣(牟良加多)郡」の中に8郷見られ、この内、当地方を指しているのは春野郷という説が有力である。
4. 中世
中世では、史料に登場する事は殆どなく、現在の町域は三俣院あるいは真幸院に含まれていたと思われます。
15~16世紀には、当時の高原は日向国と大隅国の国府付近を結ぶ要衝である事から、日向中部の伊東氏・真幸院の北原氏・薩摩国の島津氏の3氏による争いが続き、現在の市街地に位置する高原城は、3氏の勢力争いの舞台となりました。
16世紀半ばに入って伊東氏の領地となったものの、天正4年(1576)8月、島津義久・義弘ら島津勢が高原城を攻め落とし、以後島津氏の領地となりました。
豊臣秀吉の九州平定以後、島津久保、次いで島津義弘の領地となるなど変動しましたが、以後薩摩藩領として定着しました。
宗教面では、比叡山の僧侶である性空が4年間霧島で修業したという記録があります。伝承では、その性空が、後の「霧島六社権現」の基礎を作ったとしています。
また、長門本『平家物語』には、高千穂峰を「日本最初の峰」と呼んでいる部分があります。
5. 近世
薩摩藩領において確定した当初の領域は、現在の高原町(広原を除く)と都城市高崎町であったが、延宝8年 (1680)の領域変更に伴い高崎郷が分離独立し、領域減少を補う意味で、紙屋郷水流村(現都城市)と小林郷広原村(現高原町大字広原)が編入、新たな高原郷が編成され、幕末まで続きました。
藩からは地頭が派遣され郷の支配が行われましたが、度々「無地頭」という記述が見られ、地頭不在の時期があったようです。幕末には、周辺の数郷を地頭1人に一括支配させる居地頭体制が行われました。当初は小林・高原・加久藤・飯野・須木・野尻を併せた6ヶ郷請持体制でしたが、その後、小林に高原・須木・野尻・高崎を併せた5ヶ郷請持に再編成されました。この前半の6ヶ郷・後半の5ヶ郷請持体制が後の西諸県郡の基礎に繋がるものと思われます。
高原郷には、鹿児島城下から国分・霧島を経て、綾郷(宮崎県東諸県郡綾町)に至るまでの綾往還が郷内を通過していました。文化9年(1812)に日向国に測量に入った伊能忠敬一行も東御在所の麓にある祓川集落より測量を開始し、狭野神徳院に宿泊、麓村を測量しながら通過し、野尻郷との境である猿瀬越まで測量を行いました。
宗教的には、高千穂峰の周囲を囲む6つの大きな社寺を指して「霧島六社権現」と呼ばれましたが、郷内にはその2つ、霧島東御在所両所権現社・狭野権現社がありました。
6. 近代
明治時代に入ると、県域等の変更により、「高原」の範囲もたびたび変更されました。その過程で水流村や紙屋村はそれぞれ独立し、「高原」の領域は、麓・蒲牟田・広原・後川内の4村となりました。
明治16年(1883)に宮崎県が設置されると、同年6月には北諸県郡、翌17年(1884)1月からは西諸県郡に属しました。
その後、明治22年(1889)の町村制施行に伴い、麓・蒲牟田・広原・後川内の4村が合併して高原村が成立、昭和9年(1934)には町制施行に伴って町に昇格し、現在に至ります。